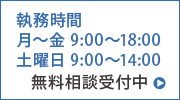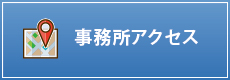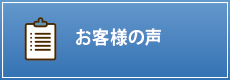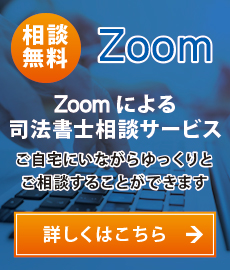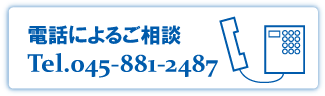�ē]�����Ƒ�������
�\ �������ق��������u������x�����ł���v���f�Ƃ́H
�� �ē]�����Ƃ́H
�����ɂ́u�ē]�����i�����Ă������j�v�Ƃ���������������Ȃ��d�g�݂�����܂��B
����́A�����l�����������F���邩�������邩�����߂�O�ɖS���Ȃ��Ă��܂����ꍇ�A���̑����l�̒n�ʂ����̎q��z��҂Ȃǂ������p�����Ƃ������܂��i���@��916���j�B
�܂�A�u�������邩�ǂ����v�����߂錠���܂ł����������̂ł��B
���Ƃ��AA���S���Ȃ�A�Z��B�������l�ɂȂ�܂����B
�Ƃ��낪B���A���������F���邩�������邩�����߂Ȃ��܂ܖS���Ȃ��Ă��܂����ꍇ�AB����̍Ȃ�q�ǂ��������ē]�����l�Ƃ���A����̑����������p�����ƂɂȂ�܂��B
�����ɂ́u�ē]�����i�����Ă������j�v�Ƃ���������������Ȃ��d�g�݂�����܂��B
����́A�����l�����������F���邩�������邩�����߂�O�ɖS���Ȃ��Ă��܂����ꍇ�A���̑����l�̒n�ʂ����̎q��z��҂Ȃǂ������p�����Ƃ������܂��i���@��916���j�B
�܂�A�u�������邩�ǂ����v�����߂錠���܂ł����������̂ł��B
���Ƃ��AA���S���Ȃ�A�Z��B�������l�ɂȂ�܂����B
�Ƃ��낪B���A���������F���邩�������邩�����߂Ȃ��܂ܖS���Ȃ��Ă��܂����ꍇ�AB����̍Ȃ�q�ǂ��������ē]�����l�Ƃ���A����̑����������p�����ƂɂȂ�܂��B
�� �������ق��������u��x�ڂ̕����v����
�ߘa6�N7��18���̓��������ٔ�������i�ߘa5�N�i���j��1976���j�́A���̍ē]�������߂��钿��������ł��B
�ƒ�ٔ����i���R�j�́u��x�������Ă���A�������߂ĕ�������K�v�͂Ȃ��v�Ƃ��āA���������̐\���Ă��p�����܂����B
�������A�������ق͂�����������A�u������x�̑�������������v�Ƃ������f�������܂����B
�� �ǂ������P�[�X�������̂��H
�@�`���S
�y��1�������J�n�z
A���S���Ȃ�A�����l�͌Z��B�̂݁BB�͑��������F�E�������Ȃ��܂ܔN�����o�߂����B
�A�a���S
�y��2�������J�n�z
B�����S���A�����l�͍�C��3�l�̎q�i�e�E�f�E�g�j�B
A�ɍ������邱�Ƃ���ɔ����������߁A��C�y�юq�e�E�f�́A�uA�̍ē]�����l�v�Ƃ���A�̑���������\�����āA�ƒ�ٔ����Ŏ��ꂽ�i���ꂪ��1�̕����j�B
�B�g���S
�y��3�������J�n�z
��B�̎q�g�́AA�̑�����������Ȃ��܂��S�����B
���̂��߁A�g�̑����l�i�q�j���AA�̑���������\�����āA���ꂽ�B
�C C�i�̂g�̕�j���A�u������x�����v��\������
C�́A�g�̕�ł���A�g�̈ꎟ�����l��A�̑���������������ʁAC�ɁuH�o�R�̍ē]�����l�v�Ƃ����V�����n�ʂ��������B
�����ŁAC�́uH�̗���������p�����ē]�����l�v�Ƃ��āA���߂�A�̑���������\�����Ă��i���ꂪ��2�̕����j�B
���{�����̒��ɂ́AB�i���ԑ����l�j�́u�n�����ԁi���@915���j�v���o�߂��Ă������ǂ����ɂ��Ă̒��ړI�Ȍ��y�͌�������܂���ł������AB���푊���lA�̑����l�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��܂��S�����i�n�����Ԃ��o�߂��Ă��Ȃ������j���Ƃ�O��Ƃ��Ĕ��f���\������Ă�����̂ƍl�����܂��B
�ƒ�ٔ����i���R�j�́u��x�������Ă���A�������߂ĕ�������K�v�͂Ȃ��v�Ƃ��āA���������̐\���Ă��p�����܂����B
�������A�������ق͂�����������A�u������x�̑�������������v�Ƃ������f�������܂����B
�� �ǂ������P�[�X�������̂��H
A �� B �� �g �Ƒ������A�����A3����ɂ킽��u�ē]�����v����������
��������Đ������܂��B�@�`���S
�y��1�������J�n�z
A���S���Ȃ�A�����l�͌Z��B�̂݁BB�͑��������F�E�������Ȃ��܂ܔN�����o�߂����B
�A�a���S
�y��2�������J�n�z
B�����S���A�����l�͍�C��3�l�̎q�i�e�E�f�E�g�j�B
A�ɍ������邱�Ƃ���ɔ����������߁A��C�y�юq�e�E�f�́A�uA�̍ē]�����l�v�Ƃ���A�̑���������\�����āA�ƒ�ٔ����Ŏ��ꂽ�i���ꂪ��1�̕����j�B
�B�g���S
�y��3�������J�n�z
��B�̎q�g�́AA�̑�����������Ȃ��܂��S�����B
���̂��߁A�g�̑����l�i�q�j���AA�̑���������\�����āA���ꂽ�B
�C C�i�̂g�̕�j���A�u������x�����v��\������
C�́A�g�̕�ł���A�g�̈ꎟ�����l��A�̑���������������ʁAC�ɁuH�o�R�̍ē]�����l�v�Ƃ����V�����n�ʂ��������B
�����ŁAC�́uH�̗���������p�����ē]�����l�v�Ƃ��āA���߂�A�̑���������\�����Ă��i���ꂪ��2�̕����j�B
���{�����̒��ɂ́AB�i���ԑ����l�j�́u�n�����ԁi���@915���j�v���o�߂��Ă������ǂ����ɂ��Ă̒��ړI�Ȍ��y�͌�������܂���ł������AB���푊���lA�̑����l�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��܂��S�����i�n�����Ԃ��o�߂��Ă��Ȃ������j���Ƃ�O��Ƃ��Ĕ��f���\������Ă�����̂ƍl�����܂��B
�� �ƒ�ٔ����̔��f
�\ �u�����������Ă��邩��s�v�v
�����ƒ�ٔ�������x���́AC�̍ēx�̐\�q���p�����܂����B���R�͂����ł��B
�|�@C�͂��ł�B��ʂ���A�̑������������Ă���A���̕��������ꂽ���_�ő����l�̒n�ʂ͏��ł��Ă���B���������āA�g�o�R�ʼn��߂ĕ�������K�v�͂Ȃ��B�@�|
�܂�A�ƒ�ٔ����́u���������͈�x�ő����v�Ɣ��f�����Ƃ����܂��B
�|�@C�͂��ł�B��ʂ���A�̑������������Ă���A���̕��������ꂽ���_�ő����l�̒n�ʂ͏��ł��Ă���B���������āA�g�o�R�ʼn��߂ĕ�������K�v�͂Ȃ��B�@�|
�܂�A�ƒ�ٔ����́u���������͈�x�ő����v�Ɣ��f�����Ƃ����܂��B
�� �������ق̔��f
�\ �_��ȉ��߂Ŏ�F�߂�
�������AC�͂����s���Ƃ��čR���B���������ٔ����́A�ƒ�ٔ����̌�����������AC�̕���������Ɣ��f���܂����B
1. ���������́u�v�Ɓu���́v�͕ʖ��
���������̐\�q������Ă��A�����̌��͂����̓I�Ɋm�肷��킯�ł͂���܂���B ����A�ƒ�ٔ������p�����Ă��܂��A���̐l�͕������咣�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B ���������āA�u�p�����ׂ����Ƃ������łȂ�����A�܂����ׂ��v�Ƃ����̂��������ق̗���Ƃ����܂��B
2. �u��d�̑����l�n�ʁv�����\��
C�͌�B�̍ȂƂ��āiB�o�R�j�A�̂g�̕�Ƃ��āi�g�o�R�j�Ƃ�����̌o�H��A�̍ē]�����l�ɂȂ蓾�܂��B �ŏ��̕�����B�o�R�Ɋւ�����̂ł���A�u����A�̑����v�ł����Ă��A�@�I�ɈقȂ�n�ʂ���������邱�Ƃ͗��_�゠�蓾��Ƃ��܂����B
3. �ƒ�ٔ����̐R���́u�����ȏꍇ�̂p���v
���ق́A�ƒ�ٔ����̖������u���̔��f�ł͂Ȃ��`���R���v�Ɍ��肵�܂����B ���������̎葱�ł́A�\�q�l�̒n�ʂɍ����I�ȋ^�����������A �܂����Ă����A��Ŏ��̓I�ɑ����]�n���c���ׂ����Ƃ��Ă��܂��B
�� ���̌���̈Ӌ`
�E���������́A�ē]�����̂悤�ɏ��p�o�H�����G�ȏꍇ�A��l�̑����l�ɂ��ĕ�����̐\�q���������邱�Ƃ��m�F�����_�B
�E�ƒ�ٔ����́A���������̐\�q�����炩�ɕs�K�@�ł���Ƃ����Ȃ�����A���������̂������Ƃ��锻�f����������_�B
�E���������ɂ�����`���R���i�̉ہj�Ǝ��̔��f�i���̗͂L���j����ʂ��čl����K�v�����邱�Ƃm�ɂ����_�B
1. ���������́u�v�Ɓu���́v�͕ʖ��
���������̐\�q������Ă��A�����̌��͂����̓I�Ɋm�肷��킯�ł͂���܂���B ����A�ƒ�ٔ������p�����Ă��܂��A���̐l�͕������咣�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B ���������āA�u�p�����ׂ����Ƃ������łȂ�����A�܂����ׂ��v�Ƃ����̂��������ق̗���Ƃ����܂��B
2. �u��d�̑����l�n�ʁv�����\��
C�͌�B�̍ȂƂ��āiB�o�R�j�A�̂g�̕�Ƃ��āi�g�o�R�j�Ƃ�����̌o�H��A�̍ē]�����l�ɂȂ蓾�܂��B �ŏ��̕�����B�o�R�Ɋւ�����̂ł���A�u����A�̑����v�ł����Ă��A�@�I�ɈقȂ�n�ʂ���������邱�Ƃ͗��_�゠�蓾��Ƃ��܂����B
3. �ƒ�ٔ����̐R���́u�����ȏꍇ�̂p���v
���ق́A�ƒ�ٔ����̖������u���̔��f�ł͂Ȃ��`���R���v�Ɍ��肵�܂����B ���������̎葱�ł́A�\�q�l�̒n�ʂɍ����I�ȋ^�����������A �܂����Ă����A��Ŏ��̓I�ɑ����]�n���c���ׂ����Ƃ��Ă��܂��B
�� ���̌���̈Ӌ`
�E���������́A�ē]�����̂悤�ɏ��p�o�H�����G�ȏꍇ�A��l�̑����l�ɂ��ĕ�����̐\�q���������邱�Ƃ��m�F�����_�B
�E�ƒ�ٔ����́A���������̐\�q�����炩�ɕs�K�@�ł���Ƃ����Ȃ�����A���������̂������Ƃ��锻�f����������_�B
�E���������ɂ�����`���R���i�̉ہj�Ǝ��̔��f�i���̗͂L���j����ʂ��čl����K�v�����邱�Ƃm�ɂ����_�B
�� �ē]�����@�\�����I�ȃ|�C���g
�܂��A���������ɂ́u�n�����ԁv�ƌĂ��3�����̊���������܂��i���@915���j�B
���̊��Ԃ́A�u�����ɑ������J�n�������Ƃ�m�������v���琔���n�߁A
�����A���̊��ԓ��ɑ�����������邩�����߂Ȃ���Ȃ�܂���B
����A�ē]���������������ꍇ�́A�������[�����ς��܂��B
���Ԃ̑����l�i���Ƃ���B�j���A���F�E���������Ȃ��܂ܖS���Ȃ����Ƃ��A
���̑����l�i�a�j�̑����l�i�a�̍Ȃ�q�j�́AB�������Ă����uA�̑������ǂ����邩�v�Ƃ����I�����������p���܂��i���@916���j�B
���̂Ƃ���3�����̃J�E���g�́A�P��B�̎��S��m�������ł͂Ȃ��A
�uA�̑����������������p������ɂ���v�ƔF�����������N�Z�_�ɂȂ�̂�������̗����ł��B
�܂�A��1�����Ƒ�2�����̏n�����Ԃ͂��ꂼ��ʌɐi�s����Ƃ��錩���ł��B
�܂��A�ē]�����l����������ꍇ�i��FB�̍ȂƎq�ǂ������j�́A
���ꂼ�ꂪ�Ɨ����ĕ����⏳�F��I���ł��܂��B
���̕����̌��͂͐\�q�������{�l�ɂ̂A�����A���������l�������u�ŏ����瑊���l�łȂ��������́v�ƈ����A���̌��ʂ͑��̑����l�ɂ͉e����^���܂���B
���̂悤�ɁA�ē]�����ł�
�@ �n�����Ԃ̋N�Z�_���u�ē]�����l���ꂼ��̔F�����_�v����n�܂邱�ƁA
�A �����̍ē]�����l�̔��f���݂��ɓƗ����Ă��邱�ƁA
��2�_���������邱�Ƃ��A������ƂĂ��d�v�ł��B
�ȏ�
���̊��Ԃ́A�u�����ɑ������J�n�������Ƃ�m�������v���琔���n�߁A
�����A���̊��ԓ��ɑ�����������邩�����߂Ȃ���Ȃ�܂���B
����A�ē]���������������ꍇ�́A�������[�����ς��܂��B
���Ԃ̑����l�i���Ƃ���B�j���A���F�E���������Ȃ��܂ܖS���Ȃ����Ƃ��A
���̑����l�i�a�j�̑����l�i�a�̍Ȃ�q�j�́AB�������Ă����uA�̑������ǂ����邩�v�Ƃ����I�����������p���܂��i���@916���j�B
���̂Ƃ���3�����̃J�E���g�́A�P��B�̎��S��m�������ł͂Ȃ��A
�uA�̑����������������p������ɂ���v�ƔF�����������N�Z�_�ɂȂ�̂�������̗����ł��B
�܂�A��1�����Ƒ�2�����̏n�����Ԃ͂��ꂼ��ʌɐi�s����Ƃ��錩���ł��B
�܂��A�ē]�����l����������ꍇ�i��FB�̍ȂƎq�ǂ������j�́A
���ꂼ�ꂪ�Ɨ����ĕ����⏳�F��I���ł��܂��B
���̕����̌��͂͐\�q�������{�l�ɂ̂A�����A���������l�������u�ŏ����瑊���l�łȂ��������́v�ƈ����A���̌��ʂ͑��̑����l�ɂ͉e����^���܂���B
���̂悤�ɁA�ē]�����ł�
�@ �n�����Ԃ̋N�Z�_���u�ē]�����l���ꂼ��̔F�����_�v����n�܂邱�ƁA
�A �����̍ē]�����l�̔��f���݂��ɓƗ����Ă��邱�ƁA
��2�_���������邱�Ƃ��A������ƂĂ��d�v�ł��B
�ȏ�
�i�o�T�F���������ٔ����ߘa6�N7��18������E����^�C���Y1532��75�Ł^�����2624��39�Łj
�i�@���m��������������
�����E�⌾�E�M���Ɋւ��邲���k�́A���C�y�ɂ����k���������B